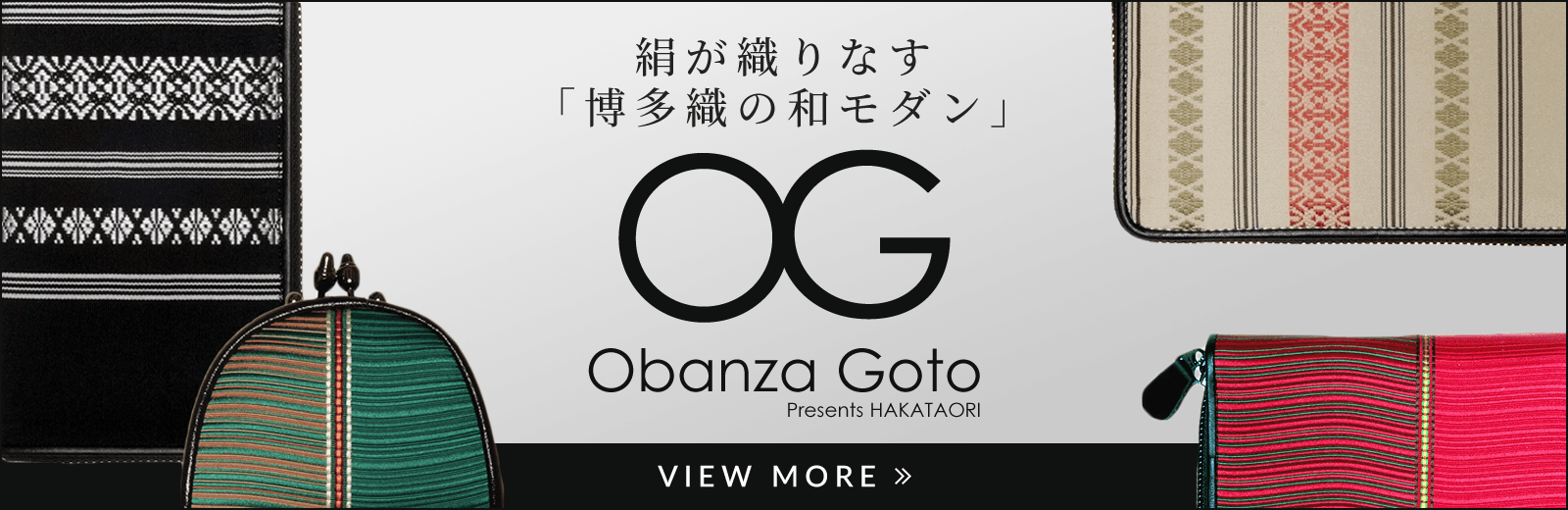取扱商品

博多人形の由来
博多は古くから、東アジアなどの大陸と交流の歴史があり、博多織や博多人形といった工芸品にもその影響がみられます。素焼きの人形を愛でる習慣は発掘調査の成果により明らかになり、約800年前の鎌倉時代、博多、鎌倉の華僑街や寺社を中心に始まったことがわかりました。その後、関ヶ原の合戦で活躍した黒田長政の筑後入国に伴って多くの職人が集められ、その職人たちによって現在の伝統工芸の下地がつくられたといわれています。江戸時代後半に正木宗七(宗七焼)や、中の子吉兵衛、白水武平といった名工達が活躍して業界は著しく注目され全国に流通するようになりました。現在では、明治の後、パリなどの国際的な博覧会で高い評価を受け日本を代表する人形として「博多人形」の名で知られるようになり、海外へも輸出されています。

博多人形の
特性と種類
博多人形の題材がバラエティに富んでいると言われるのは、それぞれが持つ独自の趣・様々な変化に合わせて作品へ昇華する為の常日頃の研究努力によるものです。
日本画、彫刻等から学びとる芸術性への姿勢は博多人形の性格に大きな影響を与えているのです。
【美人もの】【歌舞伎もの】【能もの】
【節句もの】【黒田武士】【相 撲】
【縁起もの】【高 砂】【童もの】
| お支払い方法 | ●銀行振り込み(先払い) ●郵便振替(先払い) ●クレジットカード払い |
| お支払期限 | 銀行振り込みと郵便振替:ご注文確定後7日以内。 |
ご利用可能なクレジットカード